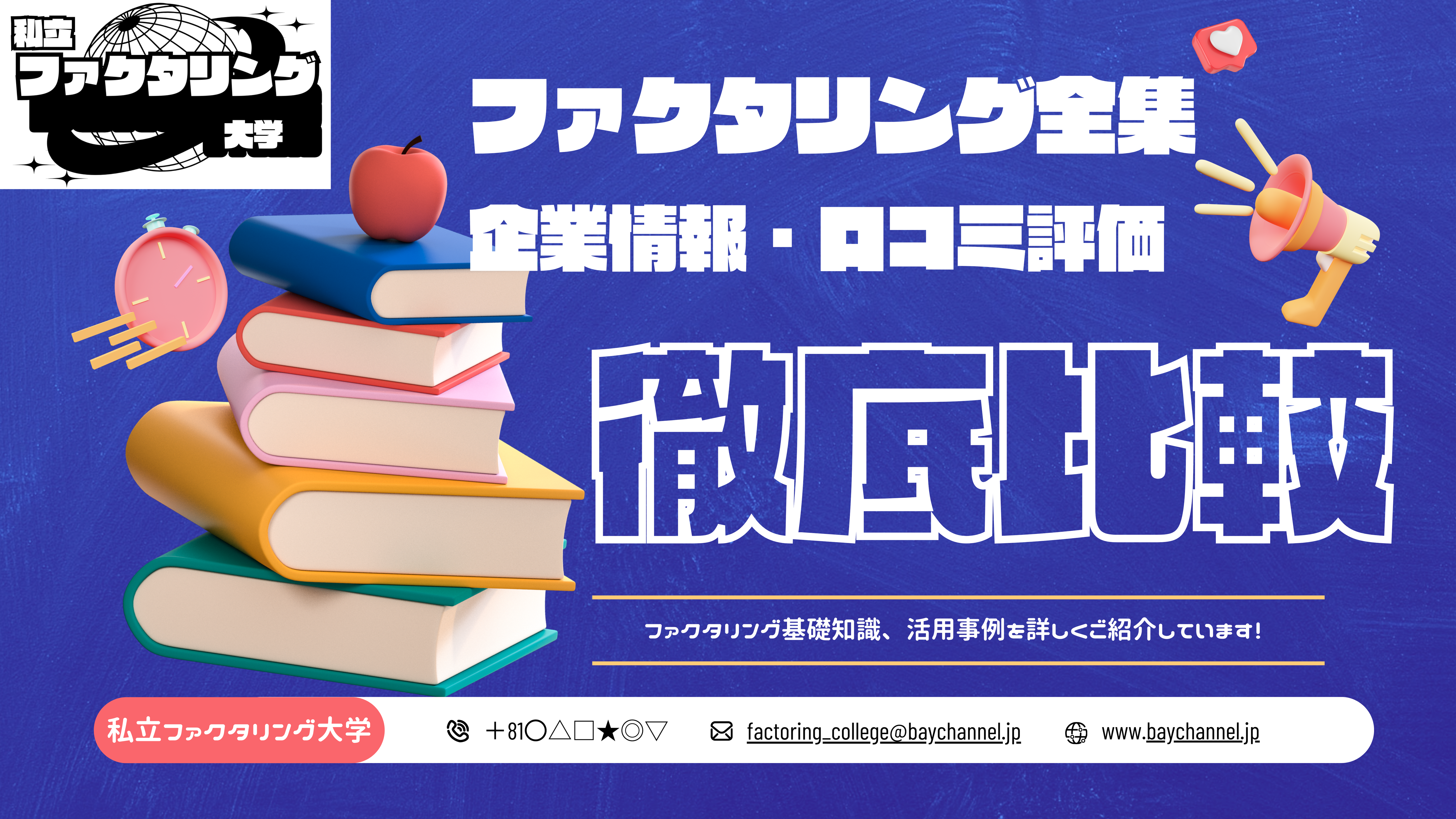ファクタリングは中小企業にとって便利な資金調達手段ですが、その一方で利用者側の不正やトラブルも少なくありません。特に2社間ファクタリングでは、虚偽の申告や債権の二重譲渡、さらには架空債権の持ち込みといったリスクが指摘されています。
この記事では、ファクタリング契約時に起こり得る重大な4つのトラブルと、その背景にある制度上の問題を詳しく解説しています。
🔍 なぜファクタリング利用者によるトラブルが起こるのか?
- 2社間ファクタリングの性質によるもの
売掛先への通知がないため、悪意のある取引をファクタリング会社が見抜きにくい構造になっている - 融資を受けられない事業者が多く利用する手法であるため、切羽詰まった状態で不正に走る可能性が高い
- 制度・法整備が不十分であることもリスク要因
❌ 利用者が起こす4つの重大トラブル(法的リスクあり)
① 審査時の虚偽申告
→ 売掛先の与信や金額などを偽って申告することで、契約自体が無効となり、損害賠償請求に発展する恐れあり。
② 債権の二重譲渡
→ 同一の売掛債権を複数のファクタリング会社に売却する行為。悪質なケースでは詐欺罪や背任罪の対象にも。
③ 入金された売掛金の横領
→ 売掛金が入金された後にファクタリング会社へ送金せず、別用途で使用すると、刑法上の横領罪に問われる可能性がある。
④ 架空債権の持ち込み
→ 実在しない取引や請求書を作成し、架空の売掛債権として持ち込むケース。これは明確な「詐欺行為」であり、刑事告訴も免れない。
⚠ 2社間ファクタリングのリスクを軽減するための対策
- 契約書・取引履歴・請求書・発注書など、実在性を証明する書類を常に整えておくこと
- ファクタリング会社との信頼関係を築き、正直な申告を徹底する
- 資金繰りが厳しい場合は、ファクタリングのみに頼らず、公的支援や融資など他の手段も検討する
✅ まとめ|ファクタリングは誠実な利用が前提。虚偽申告や二重譲渡は経営リスクに直結
- 架空債権や二重譲渡などの不正行為は、刑事事件にも発展する重大リスク
- 正規のファクタリングを有効活用するには、信頼と透明性が不可欠
- 少しでも不安がある場合は、信頼できる専門業者や弁護士への相談が推奨されます